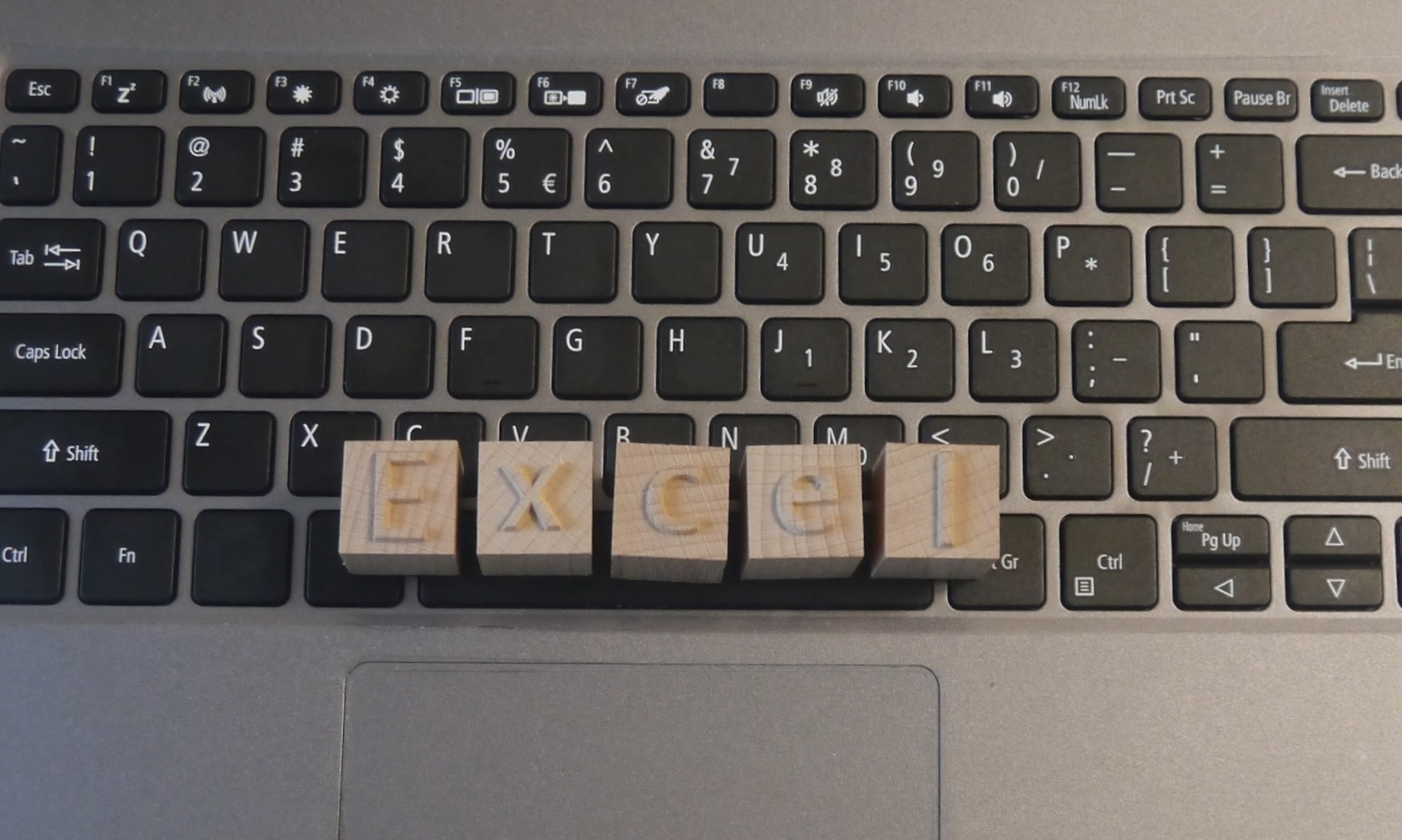国際人権ルールを考慮した就業規則の見直しについて
column
2025年09月17日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
近年、企業活動において「国際人権ルール」への対応が重要視されており、特に、減給処分を廃止とする懲戒処分制度の見直しが求められています。社労士もILOの協力を得て「ビジネスと人権」に取り組んでいます。今回は、国際的な人権規範の一つである『RBA行動規範』に関して、そのポイントと就業規則の見直しを中心にご紹介いたします。
減給処分の廃止が進む背景
懲戒処分制度を見直して「減給」を廃止する企業が増えています。日本では労働基準法に基づき制限付きで実施が認められている減給処分ですが、国際的な人権規範に照らすと「強制労働」に該当する可能性があることが指摘されており、国際的には批判の対象となりかねません。
こうした背景から、国内企業も「日本ルール」ではなく、グローバルスタンダードである『RBA(Responsible Business Alliance:責任ある企業同盟)行動規範』に沿った制度設計への移行が求められています。電機メーカーをはじめ国際基準に合わせる機運が高まっており、各社は減給処分を含め懲戒制度全体のバランスを整えることが課題となっています。
『RBA行動規範』とは
RBA行動規範とは、2004年に米ヒューレット・パッカードやIBMなどの世界的電機メーカーが中心となって策定した国際的な産業基準です。2025年8月現在では、リコー、キャノン、ソニーグループ、エヌビディア、ハイセンスなど国内外の250社以上が加盟し、業種も自動車、玩具などに広がっています。
この規範は、労働基準、安全衛生、環境保全、倫理の4分野において人権保護を求めるものであり、「ビジネスと人権」への対応が求められる中、加盟企業は自社の実情に照らして、行動規範を企業における行動方針や人権方針に落とし込んでいます。
減給処分の廃止と企業の対応
RBA行動規範では「懲戒処分としての賃金控除は禁止」と明記されており、これに準拠しない企業は、ESG(環境・社会・ガバナンス)評価の低下や取引停止などのリスクを負う可能性があります。また、SDGsへの取り組みを重視する顧客からの評価にも影響することでしょう。
実際に、キャノンは2021年にRBA行動規範をサプライヤー行動規範として採用し、CSRガイドラインを置き換え、自社の就業規則から減給規定を削除しているようです。
実務上の影響と裁判例
一方で、日本企業では、けん責→減給→出勤停止→懲戒解雇のように段階的な懲戒処分が一般的であり、「減給」は中間的な処分として位置付けられてきました。厚生労働省のモデル就業規則には次のような規定例が記載されています。
(モデル就業規則の規定例抜粋)
第○条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責………始末書を提出させて将来を戒める。
②減給…………始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
③出勤停止……始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④懲戒解雇……予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
なお、従業員の規律違反行為に対しては、次の裁判例からも、懲戒処分を段階的に重くしていく対応が望ましいです。
例1:日経BPアド・パートナーズ事件(東京地裁,2023年11月15日)では、会議への参加や業務引継ぎ等の業務命令に応じない従業員について、「けん責→減給→出勤停止→退職勧奨→解雇」とした流れが、社会通念上相当であり「解雇有効」と判断されました。
例2:カジマ・リノベイト事件(東京地裁,2001年12月25日)は、上司の業務指示に従わない女性社員を4回のけん責処分を経て普通解雇した事案で、第一審の裁判所は「解雇無効」とされ、その理由の一つに「就業規則にけん責処分より重い懲戒処分として減給や出勤停止の処分が定められているのに、これらの懲戒処分を経ずに解雇している」ことを挙げています。(なお、控訴審(東京高裁,2002年9月30日)では判断が変更されています。)
減給廃止と就業規則の見直し
減給処分を廃止する場合であっても、前述の事例のように、従業員の規律違反行為に対しては懲戒処分を段階的に重くしていく対応が重要です。そこで、就業規則については、次のような規定案が考えられます。
(就業規則の見直し例)
第〇条 会社は、従業員が懲戒事由のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
①けん責………始末書を提出させて将来を戒める。
②出勤停止……始末書を提出させるほか、○労働日を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
③降格・降職…始末書を提出させるほか、役職または職位を引き下げる。
④諭旨退職……勧告後7労働日以内に退職届を提出させる。退職届の提出がない場合は懲戒解雇とする。
⑤懲戒解雇……予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
出勤停止処分については、賃金控除ではなく、就業しない期間に賃金が発生しないためRBA行動規範に抵触しません。従業員の規律違反行為の程度に応じて、出勤停止日数を調整できますので、「出勤停止1日の処分」→「出勤停止10日の処分」などの段階的な運用も可能です。
降格・降職処分ついては、役職変更に伴う賃金減額であって、賃金控除ではないため、RBA行動規範に抵触しません。
その他、「追加研修の受講」や「業務改善プログラムの実施」など、改善に向けた措置の検討も有効であると考えます。
その他の対応が必要な項目
RBA行動規範では、減給処分の禁止以外にも、次のような規範が示されています。
- 退職の自由:「労働者は妥当な通知をすれば、いつでも自由に退職でき、罰則は科されない」と記されています。日本では民法627条および628条に基準が設けられていますが、RBA行動規範に照らして、特に有期雇用者との間の雇用契約においては、契約期間中であっても退職ができるようなルールを設けるよう検討が必要でしょう。
- 週単位の労働時間管理:「緊急事態または以上な状況を除き、時間外労働を含む週間労働時間は60時間を超えないものとする」とされています。日本では、時間外労働は原則として月45時間までとされていますが、RBA行動規範に準拠するためには、週単位での管理が求められます。
- 差別禁止規定の整備:人種・年齢・性別(性的指向や性同一性)・宗教・障害・婚姻状況などに基づく差別やハラスメントを禁止するとともに、明確に定義、伝達されるべきとされています。RBA行動規範にかかわらず、就業規則の懲戒事由としてこれらの差別禁止規定を追加すべきでしょう。
- 外国人労働者:母国語または理解できる言語で雇用契約を提示すべきとされています。
- 学生・インターン・試用期間中の賃金:同等業務の初級労働者と同水準以上にすべきことが示されています。試用期間中の賃金を低く設定している場合や、無給のインターンを実施している場合には、注意が必要です。
おわりに
RBA行動規範への対応は、単なるリスク回避ではなく、企業の持続的成長や社会的評価の向上にもつながります。「ビジネスと人権」が注目されている中、今後は、サプライチェーン全体での人権尊重が求められることとなるでしょう。国際人権ルールへの注意を払い、減給処分の廃止を契機として、就業規則の見直しや社内制度の整備をご検討いただくタイミングかもしれません。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
社労士コラム懲戒制度の実態と運用事例