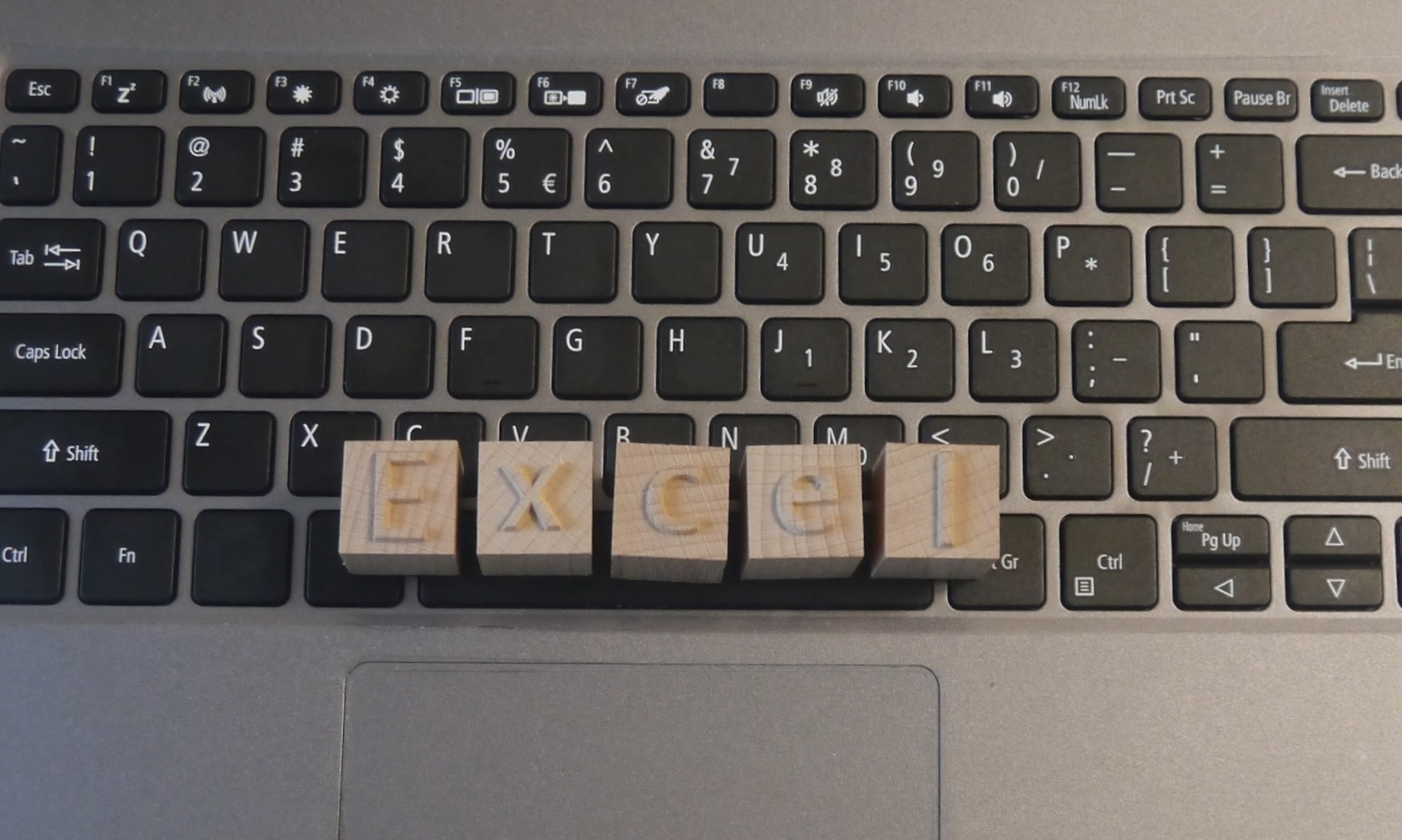社員専用のWebサイト<社内ポータル>を導入するだけで、日々の業務に必要な情報を1ヶ所にまとめられます。報連相がスムーズになって、業務効率化に成功した事例が続々と報告されています。ただし、社員が「使いにくい」と感じるツールは放置される運命をたどることになるため、注意が必要です。
今回は社内ポータル導入の成功事例を参考に、うまくいく実践法をお伝えします。
社内ポータルの導入目的を確認
社内ポータルを導入する目的をハッキリさせておくと、狙う効果を得やすくなります。
社内ポータルは業務効率化ツール
自社専用のWEBサイト、社内ポータルは情報共有を効率化するために欠かせないツールです。
壁掛けの掲示版やホワイトボードの代わりに導入するケースが目立ちますが、単純な“お知らせの場”として使うだけでは、惜しい使用方法になります。
性能の高い社内ポータルなら、業務効率化ツールとして幅広い範囲で活用できます。
実際、社内ポータルの導入によって「ペーパーレス化が進んだ」、「リモートワークしやすくなった」といった成功事例が増えています。
最終的に複数ツールをまとめて情報・運用・管理を一元化することを視野に入れ、高機能タイプの社内ポータルを選びましょう。社内ポータル機能が搭載されたグループウェアも人気です。
優先順位は?目的の明確化
社内ポータルのメリットを最大限に引き出すためには、導入の目的を明確化することが重要です。
目的を一言でまとめると「業務効率化」に他なりませんが、より具体的なビジョンを共有するためにも、社内の課題をピックアップするプロセスからとりかかるのがポイントです。
情報共有の効率化、コミュニケーションの活性化、テレワークやペーパーレス化の推進、コスト削減・・・など解決したい問題を拾い上げ、重要性・緊急性によって序列をつけます。
社内ポータルの強みは各社差があるため、課題に優先順位をつけることで自社のニーズにマッチするサービスを選びやすくなります。
成功事例で見る6つの実践法
せっかく社内ポータルを導入したのに、うまく活用できないと投資した費用がムダになりかねません。そこで、成功事例に共通する実践のコツをくわしく解説しました。
社内ポータルの運用担当を選出
社内ポータルをスムーズに浸透、定着させるためにも、早い段階で運用の担当者を決めるのが効果的です。
ITスキルを持つ人材を選出し、システムの管理やメンテナンス、トラブルシューティングの対応を任せます。運用マニュアルを作成する担当も決めなくてはなりません。
とくに導入当初は、社員から使用方法について度々質問が寄せられるため、フォローアップのための問い合わせ担当も必要です。
情報の周知、効果的に情報を発信するのも、運用を軌道に乗せる大事な役目です。IT人材が乏しい場合、サポート力重視で契約するサービスを選びましょう。
全社員に周知
社内ポータルを“なんとなく”導入するのはNGです。初期段階のアクションが成功の鍵を握っているため、全社員を対象に導入目的をしっかり説明するのがファーストステップになります。
通常業務と並行して新しいツールの操作方法を覚えるために、社員は時間とエネルギーを費やさなくてはなりません。使うメリットがあることをきちんと理解していないと、乗り気になれないものです。
また、効率がわるくても「使い慣れたツールのほうがいい」と思っている社員もいるかもしれません。
必要に応じて、情報一元化やペーパーレス化の重要さを認識するための研修や、操作方法の研修を実施することで、苦手意識を取り除きましょう。
活用しない機能を「隠す」成功事例も
ぱっと見て「むずかしそう」と感じる見た目だと、ITリテラシーの低い社員の抵抗感を払拭できません。
社内ポータルには情報・機能が集約されていますが、使わない機能はあえて表示しないことがプラスに働いたケースも少なくありません。
メニューや画面の設定で、表示する機能は選択できます。シンプルで使いやすそうな見た目にすることも、社内ポータルのアクセス数を増やすのに有効な戦略の1つです。
コミュニケーションルールの策定
社内ポータルは社員同士のコミュニケーションツールとして活用できますが、不要なトラブルを避けるためにも、コメントやフィードバックのルールをあらかじめ策定しておきます。
所属部署の明示やアカウント名の表示形式を統一する・・・といったルールがあれば、
快適に利用できる環境を整備しやすくなります。
勤務時間外に頻繁にお知らせがくるのも社員のストレスになるため、利用時間帯も制限します。アクセスできる時間帯を使いわけることで、業務時間外の不正アクセス、情報漏えいリスクにも備えられます。
アクセス数を決めるマルチデバイス機能
社内ポータルを選ぶときは、マルチデバイス機能は必須条件になります。スマホやタブレットで使えなければ、アクセス数も伸びません。
アンドロイド端末で使えない社内ポータルもあるので、利用できない場合は代替手段を考えなくてはいけません。
端末のOSバージョンをアップデートすることで対応可能になることもあります。
いずれにしても、こういった対応を個人任せにするのではなく、運用担当側が主導して、適宜フォローしていくことが大切です。
トライアルサービスも重要
社内ポータルサイトの使いやすさは、実際に操作してみないとわかりにくいものです。現場で「使いやすい」と実感できるサービスを選ぶためにも、トライアルサービスが利用できると安心です。
同じ職場でも、ITリテラシーにはかなりの差があるはずです。実際に操作してもらった上でアンケートを取るなど、導入前から現場の声をピックアップする作戦も有効です。
表示速度や検索しやすさも、実際に試用しないと判断しにくいポイントになります。
操作性の他、機能やセキュリティ、既存システムや他社サービスとの連携性もチェックした上で、自社に最適な社内ポータルか見極めてください。
【1人220円/月(税込)】J-MOTTOなら全26機能が使い放題
社内ポータルの導入にはお金がかかりますが、セキュリティの観点からも無料サービスは避けたほうが無難です。
有料サービスの中でもグループウェア<J-MOTTO>は、高度な運用環境と安全対策で定評のあるリスモン・ビジネス・ポータル株式会社のサービスなので、安心です。
低予算のツール革命を実現
月額の使用料が1人220円(税込)しかかからないJ-MOTTOなら、低予算のツール革命を実現できます。
掲示板に情報を掲載するときもカテゴリを細かく分けられるため、全社員向け・プロジェクトメンバー向け・・・と対象者を絞って情報を発信可能です。
社内SNSの役割を果たすネオツイ、回覧・レポート、電子会議室、アンケート機能など社内の情報共有とコミュニケーションを円滑にする機能が一通りそろっています。
ワークフロー機能やスケジュール管理機能など、全26機能を基本料金だけで使えるため、ツールの統合を目指す会社のニーズにもマッチします。
月額220円(税込)〜使えるグループウェア「J-MOTTO」の詳細はこちら
導入前から視聴OK!無料WEBセミナーも充実
J-MOTTOはサポート体制が手厚く、導入前から寄り添ってくれます。無料WEBセミナーも契約前から視聴OKで、最大3ヶ月ものトライアル期間があるのも安心材料です。
導入後も、全ユーザーが電話・メール・チャットで問い合わせできるサポートセンターを利用できるため、IT人材が乏しい会社からも支持されています。
現在、中小企業を中心に4,000社・14万人がJ-MOTTOを活用していますが、業務効率化ツールを初めて利用する企業も少なくありません。
自社仕様にカスタマイズ可能(有料オプション)
J-MOTTOはカスタマイズ性も抜群です。有料オプションも充実しているので、必要に応じて、より専門性の高い機能を追加できます。
交通費・経費精算機能も需要の高いサービスで、あとから追加する企業が増えています。自社仕様にカスタマイズし、社内の課題にマッチするツールに最適化しましょう。
あとから容量を増やすこともできるので、拡張性も申し分ありません。
グループウェアを導入すると各方面で業務効率化が進むため、今後、事業が拡大する確率が高くなります。
必要な機能やユーザー数が増えても即座に対応できるので、ライバル企業に差をつける競争力の向上にもつながるはずです。
社内ポータルとして使いやすい「J-MOTTO」の詳細はこちら