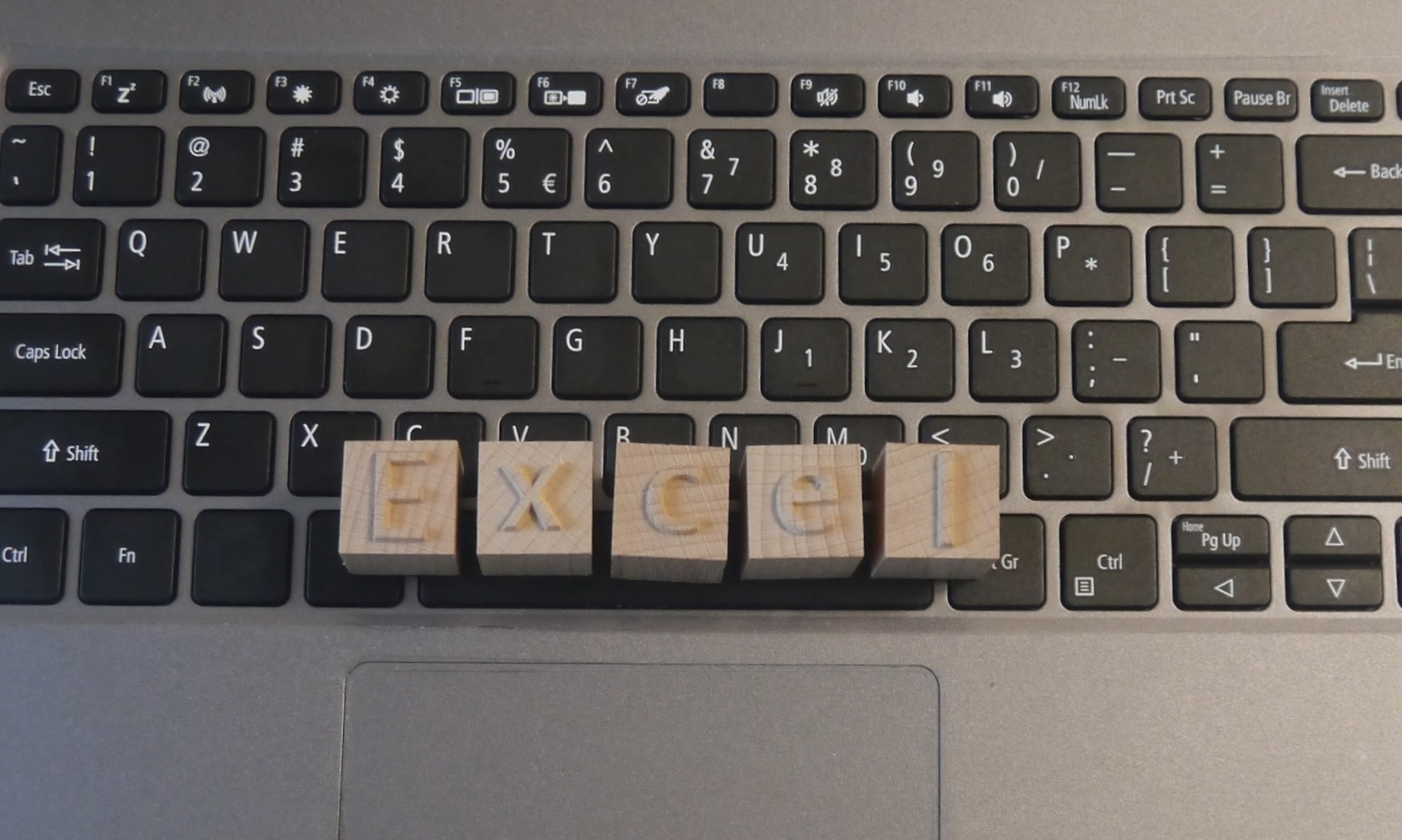年金制度改正のポイント
column
2025年07月16日
社会保険労務士法人味園事務所 代表社員所長 味園 公一
今回は、社会経済の変化を踏まえた持続可能な年金制度構築を目的として、2026年より順次施行される「年金制度改正法」のうち、企業の人事労務管理に直接関係する主要改正点についてご紹介します。
制度改正の背景
少子高齢化や人口減少のほか、単身世帯や共働き世帯の増加、働き方の多様化(副業・兼業、フリーランス、女性や高齢者の就労の進展)等による社会経済の変化に対し、年金制度の持続可能性が課題となってきました。
働き方や男女の差に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化に合わせた柔軟な制度設計を行うことが求められることから、性別による年金制度の格差を是正するほか、高齢者の就業促進と年金受給の両立を支援するとともに、高所得者の保険料負担強化や所得格差の是正を図るための基礎年金の給付水準の底上げが実施されます。
主な改正内容
年金制度改正の主な内容は次の通りです。
- 社会保険の加入対象の拡大
- 在職老齢年金の見直し
- 遺族年金の見直し
- 標準報酬月額の上限引上げ
- 将来の基礎年金の給付水準の底上げ
社会保険の加入対象の拡大
現行では、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象となっています。短時間労働者の加入要件は、次の通りです。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
今回、短時間労働者の加入要件が見直され、月額8.8万円以上の賃金要件(いわゆる「106万円の壁」)が撤廃されます。また、現状51人以上とされる企業規模要件も2027年から段階的に撤廃され、最終的に2035年以降は10人以下の企業も加入対象となります。これにより、週20時間以上勤務する方(学生を除く)は、企業規模に関係なく順次社会保険への加入対象となります。
また、これまで非適用とされていた「常時5人以上の者を使用する個人事業所」の一部業種(農業・飲食業等)についても、2029年より原則適用対象となります。
制度改正により新たに社会保険の対象となる短時間労働者について、被保険者負担分の保険料を事業主が追加負担した場合に対し、国の支援措置が導入される予定です。 実務対応としては、新たに社会保険の対象となる従業員の抽出や保険料試算を実施し、従業員への事前案内をしましょう。また、就業規則や雇用契約書等の見直しが必要となる可能性があります。
在職老齢年金の見直し
在職老齢年金制度とは、年金を受給しながら働く方の賃金と老齢厚生年金の合計が基準(支給停止調整額)を超える場合、老齢厚生年金が減額される制度です。この支給停止調整額が51万円から62万円に引き上げられます。
厚生労働省の試算によると、制度改正により、約20万人が新たに老齢厚生年金の全額受給可能となる見通しとのことです。
現行では在職老齢年金の仕組みを意識して、定年再雇用時等に労働時間を減らす動きが見受けられますが、制度改正により働きながら年金を受給する人のいわゆる「働き損」が軽減され、高齢者の就業促進及び企業の人材不足解消にも一定の効果が期待されます。
遺族年金の見直し
現行の遺族厚生年金制度では、配偶者を亡くした場合の受給要件に男女差があります。女性(遺された妻)は30歳未満で死別であれば「5年間の有期給付」、30歳以上で死別であれば「無期給付」とされています。一方、男性(遺された夫)は55歳未満で死別の場合は「給付なし」、55歳以上で死別であれば「60歳から無期給付」とされています。
この制度上の格差を解消するため、すでに受給中の方に不利益が生じないよう配慮した上で、2028年から段階的な見直しが実施されます。具体的には、男女共通の要件として、60歳未満で死別であれば「原則5年間の有期給付(所得や障害の状態により配慮が必要な場合は最長65歳まで給付継続)」とし、60歳以上で死別であれば「無期給付」とされます。
また、子に支給する遺族基礎年金については、子の生活状況に応じた柔軟な支給が可能となるよう、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくしていても、子どもが遺族基礎年金を受け取れるようになります。
標準報酬月額の上限引上げ
厚生年金保険の保険料・給付の算定基準となる「標準報酬月額」の上限が、現行の65万円から75万円へ段階的に引き上げられます。具体的には、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円という3段階で引き上げが実施されます。
高所得者においては、保険料負担が増加する一方、将来の年金給付額も増加します。役員報酬や高額給与者の報酬設計に影響があるため、給与改定や賞与支給額におけるシミュレーションが重要です。
将来の基礎年金の給付水準の底上げ
「マクロ経済スライド」とは、2004年の年金制度改正で導入されたもので、少子高齢化で年金受給者が増える一方、制度を支える働き手の減少を見込んで、持続可能な年金制度となるよう「年金の給付水準を調整する仕組み」です。具体的には、賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を差し引くことによって、年金の給付水準を調整(調整分は将来へ向けて積立)します。
厚生労働省の試算によると、現行制度で基礎年金と厚生年金のそれぞれでマクロ経済スライドによる調整を行った場合、厚生年金については早期に調整が終了するのに対し、基礎年金については調整の終了が大きく遅れ、その結果、基礎年金の支給額が大きく下がってしまうとのことです。
そこで、今回の改正法では、「2029年の次回財政検証で基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には底上げ策を実施する(基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制措置を講ずる)」と法案の付則に明記されています。これにより、2029年の財政検証の結果により、2030年の次回年金制度改正で「基礎年金底上げ案」が実現される可能性があります。
おわりに
今回の制度改正では、段階的な企業規模要件の撤廃により、これまで適用対象外だった中小企業や個人事業所も、社会保険の加入義務が生じるようになります。短時間労働者を多く雇用し、社会保険適用対象外だった業種においては、今後の段階的適用によって人件費管理や労務管理への影響が避けられません。事前に従業員への制度周知を行うことや、保険料負担を考慮した人件費設計を行う必要があります。
また、「基礎年金の底上げに厚生年金の積立金を活用する」という方針に対しては、「厚生年金を削って基礎年金に充てられる」「会社員の納付した保険料が他者に配られる」という誤解が拡散される可能性があり、企業としても従業員からの問い合わせに備えて正確な情報を把握しておくことが大切です。
- 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
- この情報の著作権は、執筆者にあります。
- この情報の全部又は一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。
関連コラム
社労士コラム老齢年金の繰下げ制度について